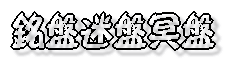
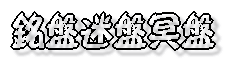
|
第4回 交響曲第7番イ長調作品92(ベートーヴェン) 4回目にしてやっと普通の内容か?(笑)。ベートーヴェンの交響曲で最も好きな曲です。 内容的には8番ヘ長調ほどでは無いけど少々軽め、「英雄」や「合唱」ほど長くもなく至極適当。よってさほど聴き疲れしません。そしてこの曲の特徴は全曲を貫く躍動感。リズムがはっきりしているというのはウケる要因の一つのはずですが、知名度はベートーヴェンとしてはおそらく真ん中くらいでしょうねぇ。ニックネームのある「英雄」「運命」「田園」「合唱付」には多分負けます。 初演は1813年12月8日とのことですがそのとき第二楽章がアンコール演奏されてます。手元には十数種の演奏がありますが今回は5種ほど出します。 |
|
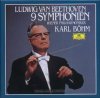 |
カール・ベーム指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団(DG POCG−90468/73) 1970〜72年の全集で72年9月録音。私のデフォルトですね。この録音を初めて聴いてから四半世紀経ちますが未だに愛聴。 |
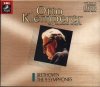 |
オットー・クレンペラー指揮、フィルハーモニア管弦楽団(EMI CC30−3272〜77) 1957〜60年の全集で60年10〜11月録音。かなり遅いテンポです。遅い演奏は緊張感が途切れる物も多いのですがこれは緊張が持続します。宇野功芳は「情熱の氷づけ」と評してますね。第二楽章(非常に遅い)のエンディングで弦がpizz.のまま終わりますが、この表現はエーリッヒ/カルロス・クライバー親子の録音にも見られるそうです(なぜか未聴)。 |
 |
セルジュ・チェリビダッケ指揮、ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団(METEOR MCD−042)(輸入盤) 一切の録音データ無し(^^;。(P)1993とあるからそれ以降の筈はないですけど。で、チェリですから当然のようにライブです。これも遅いテンポですが特に第一楽章はクレンペラーを凌ぐ遅さでもはやダレる寸前(ダレてるかも?!)。なんたって17分近く(主題提示部のリピート無し)かかりますし。ちなみにクレンペラーは14分、ベームは12分ちょっと、快速派?のカラヤンの63年録音(今回は無し)では11分半程度です。その第一楽章のリズム「タンタタッタンタタッ」の「タン」の部分がテヌート気味で「タータタッ」と聴こえます。 ※その後の調査(大袈裟な)により1989年1月のライブらしいということが判りました。テオさんどうもです。出典は こちら |
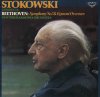 |
レオポルド・ストコフスキー指揮、ニュー・フィルハーモニア管弦楽団(LONDON(キング) K30Y 1019) 1973年1月録音。氏は69歳の時に3度目の結婚をし(嫁は19歳!)子供を2人作ったというバケモノですがこの録音も90歳の頃とは思えないほど元気です。意外といっては何ですがオーソドックスな演奏で氏の録音にありがちなオケの改変がほとんどありません。しかし独特のテンポの揺れは紛れもなく氏の物ですねぇ。この曲の特徴である第三楽章のトリオが2度出る部分をちょん切ってるのはちと気に入らないです。ちなみに氏のベートーヴェンは非常に少ないです。 |
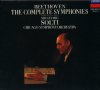 |
サー・ゲオルク・ショルティ指揮、シカゴ交響楽団(LONDON(ポリドール) POCL−9571/6) 1986〜90年の全集で88年5月録音。今回出す分ではもっとも新しい録音なのでさすがにクリアな音です。最近の傾向としてソナタ楽章の提示部を繰り返してますね。ただこれいい演奏だとは思うのですがなんか平凡でピンとこないのです。なんたってベートーヴェンだし古今東西の名演が存在するので抜きんでるのは容易でない、ということでしょうか。などと文句つけてますが「良い音で聴きたい!」と思ったときはこれになることが多いです。 |
近年ベートーヴェン研究が進み、ベーレンライター社が新しい楽譜を出してます。1999〜2000年頃録音されたアバド/ベルリンフィルの録音などその楽譜を用いているのですが未聴です。それとクライバーを未聴なのはちょっと情けないですね(^^;。クライバーのベートーヴェンは例の4番(ベーム追悼のヤツ)しか聴いたこと無いのです。 |
|