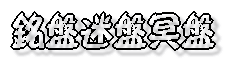
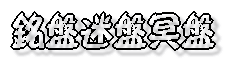
| 第9回 無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ&パルティータBWV1001−1006(J.S.バッハ) ケーテン時代の傑作です。というかバッハはこのころ続々と傑作を書いてますね。ちょっと有名な曲はこの時代に集中しているようです。で、この曲ですが長い間忘れられてました。というかバッハ自体も半ば忘れられてました。しかし19世紀のロマン派時代にメンデルスゾーンがマタイ受難曲などを蘇演し再評価され始めました。そして19世紀末にドイツのヴァイオリニスト、ヨーゼフ・ヨアヒム(1831−1907)によってこの曲が復活しました。以後音楽的にも技術的にもヴァイオリニストの目標の一つとして君臨します。 手元のCDを探したら10種ほど出てきました。適当に見繕って紹介します。 |
||
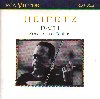 |
J.ハイフェッツ/RCA GD 87708(2)(輸入盤) 1952年10月録音。20世紀のヴァイオリン演奏のスタイルを決定づけたといわれる巨匠です。ここでの演奏はやっぱりというか豪快ですねぇ。何となくハイフェッツにこの曲は似合わない気もしますが、なんせハイフェッツです(笑)。 |
|
 |
K.ズスケ/ドイツ・シャルプラッテン TKCC−70027 1983年〜1988年録音(ずいぶんかかってるね)。ゲヴァントハウス管弦楽団のコンマスの演奏。実直、という表現がぴったりかも。もうちょっと遊んでもいい気もしますが何せバッハだし.... |
|
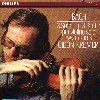 |
G.クレーメル/フィリップス 416 651−2 1980年2月〜6月録音。これはもう新時代の音ですね。とても鮮烈です。この曲に限らずクレーメルの存在自体が音色も表現も新時代なんですねぇ。 |
|
 |
S.クイケン/ハルモニア・ムンディ GD77043(輸入盤) 1981年11月〜12月録音。バロックヴァイオリンによる演奏です。前述3種はモダンヴァイオリンですから当然違う音がします。古楽・バロックとして捉えるならこういうのもありですが、ヴァイオリン音楽としてはどうなんでしょう。 |
|
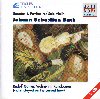 |
R.ゲーラー/アルテ・ノヴァ 74321 67501 2(輸入盤) 1998年7月録音。バッハの時代はこうだった、とばかりに湾曲した弓で演奏してます(右の写真参照)。モダンヴァイオリンの弓は日本刀のごとく逆反りしてますので3声4声同時に鳴らすことはできないのですが、こういう弓ならできます。というわけでバッハはこう弾いてほしかったんだ、ということなんでしょうが正直言って奇異に響きます。モダンでの演奏に慣れきってることもありますが、弓以外の部分(楽器とかヴィブラートとかの表現)がモダンに聞こえるのです。それとピッチも変。前述クイケンは低めでしたがこっちはモダンピッチのままなのです。弓以外は時代考証を完全に間違えてる気がしますねぇ。 |

|
クイケンには支持者もいると思いますが私はあまり好きでないです。ゲーラーはもっとイヤ。学術的には正しいのかもしれませんがねぇ(ゲーラーは学術的にも間違ってると思うぞ)。古今東西の演奏を聴いたわけではありませんが、今のところクイケンなどによるによるバロック様式での正しい演奏はハイフェッツやシェリング(今回は無し)によるモダンでの間違った演奏を凌駕したとはとても思えないのです。 バロックヴァイオリンとは、モダンヴァイオリンとは、って話は別の機会に。 |
||