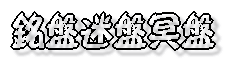
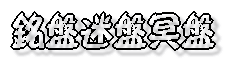
| 第11回 ジャズマンはバッハを目指す... バッハってジャズの人にも大人気です。なんでもバッハの様式性はジャズの方法論に通じる物があるそうで。そうなのかなぁ..と思いつつも盤が多いのは事実です。 ジャズ(というか非クラシック)ミュージシャンによるバッハ(というかクラシック全般)へのアプローチは 1.完全に分解して素材として使用といった感じに大別されるかもしれません。素材として使うのは私の手持ちCDではジャスよりロックに目立ちますねぇ。そんなわけで今回は2と3が多いかな。 |
|
 |
平均律クラヴィーア曲集第1巻/キース・ジャレット(Pf)/ECM POCC−1500〜1 1987年2月録音。これは先入観無しに聴いたらまずジャズピアニストの演奏だとは判らないでしょう。ジャズ的インプロビゼーションを全く行わず真摯にバッハと向き合ってます(エラソーな言い方)。というか今回紹介する中ではこれだけクラシックのコーナーに置いてあるはずです。通常のクラシック系ピアニストの演奏とも比肩しうる、あるいはこの曲の歴史的名演の一つに数えられるのでは。 |
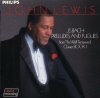 |
プレリュードとフーガ/ジョン・ルイス(Pf)他/フィリップス 32JD−26 1984年1月録音。前述キース・ジャレットと同じ曲ですが全くアプローチが違います。ここではプレリュードをほぼ楽譜通りに弾いた後インプロビゼーションを経てフーガを小編成のコンボで演奏するというスタイルでやってます。フーガの各声部を別々の楽器に当てたような編曲がなされてます。 *2001年4月1日、新聞に訃報が載りました(3月29日、80歳で死去).... |
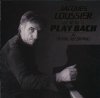 |
プレイ・バッハ/ジャック・ルーシェ(Pf)他/キング K32Y 6030 1984年12月録音。この人はバッハ・ジャズのエキスパートですね。コラールやカンタータ、管弦楽、ピアノ、オルガン、とあらゆるジャンルからピアノトリオに編曲されてます。 |
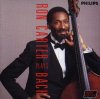 |
ロン・カーター・プレイズ・バッハ/ロン・カーター(B)/フィリップス PHCE−12007 1985年4月録音。ジャズベースの巨匠がチェロ組曲・リュート組曲をピチカート奏法のみで演奏してます。当時大絶賛されたようですが私が入手したのはもっと後です。 手法的には正統派クラシックなんですがジャズと思って聴いた方が楽しめますね。 |
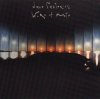 |
ワード・オブ・マウス/ジャコ・パストリアス(El−B)/WARNER BROS. 3535−2(輸入盤) 1980年頃録音。4曲目が「半音階的幻想曲」とありBWV903の「半音階的幻想曲とフーガ」の前半部をほとんどそのまま演じてます。エレキベース(但しフレットレス)ですから純クラシックとは無縁のはずなんですがここでは完全にクラシックを演奏するような感じで取り組んでます。ロン・カーターより音程も良いですしね(笑)。 鍵盤楽器用の曲をそのままエレクトリックベースで弾いてしまうテクニックって一体.... |
 |
パンプ・イット/ジェフ・バーリン(El−B)/ビクター VDJ−1055 1986年7月録音。これはロックかも。4曲目が「BACH」という曲ですが平均律クラヴィーア第2番を素材としてます。同じエレキベースですが前述ジャコとは全く異なるアプローチで、こっちはかなりアレンジ入ってます。だけどアレンジが軽めで上記ジャック・ルーシェほど楽しめません。ベーシストとしてのテクニックは凄いんですが。 |
ベース弾きだったこともあるんでなんかベースの演奏が多いですね。 1985年頃の録音が多いのはこの年がバッハ生誕300年だったからです。ちなみに昨年(2000年)は没後250年でした。これだけの歳月を経ても未だに愛される音楽って凄いですねぇ。今の音楽が2〜300年後愛されてるでしょうか.... |
|