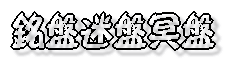
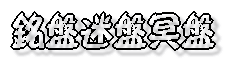
| 第15回 交響曲第9番ニ短調作品125(ベートーヴェン) ベートーヴェンは前に7番をやってますが、時期的に9番もやってしまいましょう。なんで年末に第9なのか、なんでそれが定着したのかよく分かりませんからそれには触れません(ぉぃ)。この時期以外に第9を聴くと変わり者に思われ、この時期に聴くとミーハーに思われてしまいます。こまったな...(笑)。 この曲の初演は1824年5月7日、ベートーヴェン自身の指揮で行われました(でも実際にはコンマスやサブ指揮者がコントロールしたらしい)。初演から大好評で(指揮をしたベートーヴェンは拍手が聞こえなかったというエピソードは有名)200年近く経った今でも人気を持続したままです。 この曲は既に形式的には破綻しており、第一、第二楽章こそオーソドックスなソナタ、スケルツォですが、第三、第四は変奏曲形式....なのかな....で全く自由に書かれています。そして何よりも特徴的なのが終楽章でカンタータ形式の独唱+合唱を用いたこと。これにより現在「下町のみんなで第9を歌おう」といったレベルでもそれなりに味わえるワケです。 シラーの「歓喜に寄す」に曲を付けようとベートーヴェンが考えたのはかなり昔のことといわれてます(一説によると1798年頃−30年前近く前ですね)。結局は...まぁ悪く言うと自分に都合のいい箇所だけを引用しているのですが(^^;。 手元には十数種ありますが、7番とダブらないように出しましょう。まずは絶対に外せないこれから。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮、バイロイト祝祭管弦楽団(東芝EMI CC35−3165) 1951年7月29日のライブ録音。第二次大戦後、バイロイト音楽祭再開の初日のものです。「他の第九は要らない。これだけで十分!」などという人も多い超絶演奏です。ラストなんて完全に崩壊してるんですが、そんなことはどうでもいいです。しかし流石に音が悪いな....。 フルトヴェングラーの第9は他にもありますが、1940年代のライブで第三楽章のホルンが大チョンボやってるのも妙に印象に残ってます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
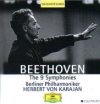 |
ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団(DG 463 088−2)(輸入盤) カラヤンは4回全曲録音をやってますが、これは2回目の1961年〜1963年もので第9は1962年10〜11月録音。カラヤンの音楽って嫌いな人は徹底的に嫌いらしいですが、一度聴いてみましょう(笑)。悪くいうとややウソっぽいらしいですが、第二楽章の狂乱は凄いですし第三楽章も思ったよりゆったりしてます...というか最近の演奏がかっとび過ぎなのかな(^^;。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
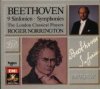 |
ロジャー・ノーリントン指揮、ロンドンクラシカルプレイヤーズ(EMI CDS 7498522)(輸入盤) 1987〜88年の全集で88年8月録音。なんとオケのメンバー一人一人の名前が載ってます。ノーリントンは古楽の人ですが、どうもこの低めのピッチが馴染めません。演奏はきびきびした最近の傾向です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
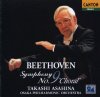 |
朝比奈隆指揮、大阪フィルハーモニー交響楽団(キャニオン PCCL−00485) 1997年7月6日のライブ。流石に上記フルトヴェングラー盤より圧倒的に録音が良いです(当たり前か)。 手元の解説によると朝比奈隆は7回全曲録音を行ってるそうで、これは6回目のものです。でもどうもワシの好みには合いません。第一〜二楽章こそ泰然としてますが、第三〜四楽章が意外と素っ気なく聴こえます。でもワシは前半2楽章だけあればいいからこれでいいのかな(^^: *朝比奈隆氏は2001年12月29日逝去しました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
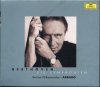 |
クラウディオ・アバド指揮、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団(DG UCCG−1003/7) 1999年〜2000年に録音された全集で第9は2000年5月録音。最大の特徴は新研究のベーレンライター社の楽譜を使ったということでしょう。21世紀のベートーヴェン表現の指標なのかも。 アバドは他にウィーンフィルとの録音も持ってるんですがそっちの旧録音が好きかなぁ...(^^;。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4回で未聴だったアバド/ベルリンがここには入ってますね(笑)。他にももう一つ全集を入手した気がするんですが、誰の演奏だったかな?(爆)。 CDのフォーマットはこの曲が基準で決まったと言われ、ネタを出したのはカラヤンということになってます。しかしカラヤンの演奏はそれほど泰然としてないので70分もかからないのですが。 泰然さ(?)ではカール・ベーム最後の録音がかなり凄いです。LPでは2枚組の各面に各楽章が入るという構成でした。多分トータルで80分超えてるんじゃないかな?残念ながらCDでは持ってません(CD見たら超えてなかった)。 それはともかく、上のコメントにもちょこちょこ書いてますが、往年の巨匠風の演奏は最近の研究ではテンポが遅すぎるらしいですね。ちょっと羅列してみましょう。 思ったより傾向がでてますね。1988年以降の録音(朝比奈を除く)で大幅に変わった感じです。スケルツォ楽章のばらつきはリピートするかしないかかな。クレンペラーは芸風が変化している時期だそうで、ちょっとバラバラなテンポですね。カラヤンとベームの第三楽章に殆ど差がないのもちょっと意外。アバドの新旧の差は凄いですが、その間に研究が進んだということでしょうか。そうなると多数録音してるカラヤンあたり全部押さえたいところです(やめとけ) 実はこれ書くため第9をずぅっと聴いてました。流石にくたびれた...(^^; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||